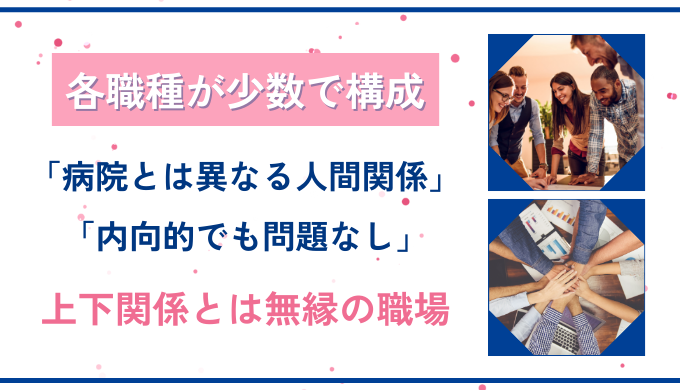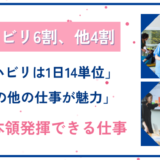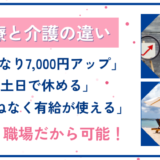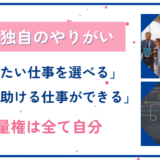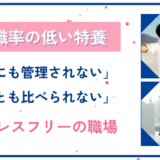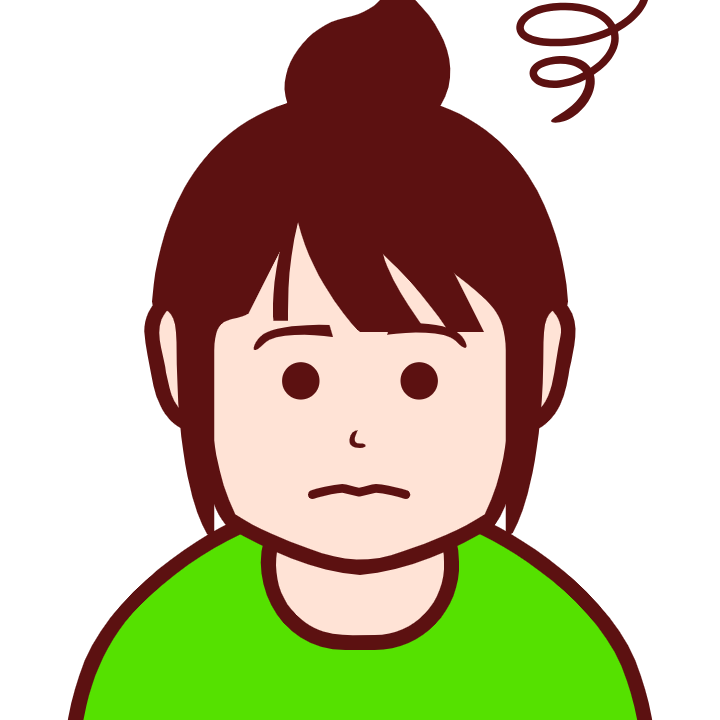
特養では、どんな職種と働くことになるの?
コミュニケーションは苦手だから不安だな。
特養では、リハ職の同僚はいません。
基本はひとり職場となります。
そのため、病院と比べると同僚との人間関係はガラリと変わります。

私も、転職するときにいちばん不安だったのが人間関係!
内向的な性格だから・・・。
実際に働いてみて分かった、病院との大きな違いは2つ。
1.上下関係がない
2.職種間の壁がない
病院との違いがでる理由は、各職種の人数と比率が異なるから。
特養では、介護士を除いて、どの職種も1人〜5人ほどの少数で構成されています。
| 職種 | CW | NS | CM | SW | 栄養士 |
|---|---|---|---|---|---|
| 人数 | 40人〜50人 | 3〜5人 | 1〜2人 | 1人 | 1人 |
多職種でより密にコミュニケーションをとる必要がある特養では、人間関係がフランクになりやすいのです。
特養は、私のような内向的な性格の人にとっては、馴染みやすい環境だと言えます♪
本記事では、特養で一緒に働く職種との関係性について詳しく紹介していきます!

特養で花開いたPT
Bすけ
ダメ出しばかりくらい続けた病院から逃げるように転職。転職先の特養では理事を任されるまでに! 働く場所が人の価値を決めるのだと実感。PT・OTが価値を見出しやすい特養の魅力を発信しています!
特養でPT・OTがよく関わる6職種と関係性

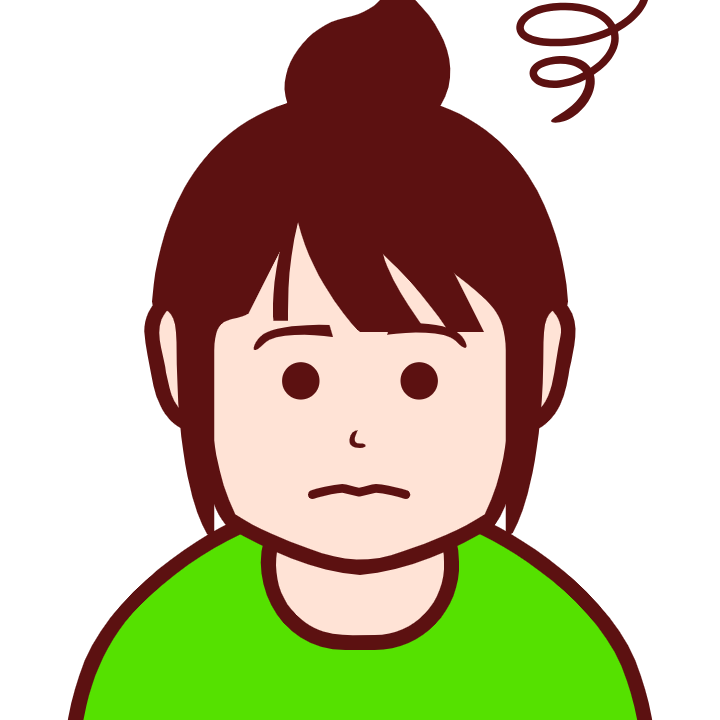
特養ではどんな職種がどれくらいいるの?
PT・OTがよく関わる職種は?
主に関わる職種と人数構成は以下のとおり。
| 職種 | CW | NS | CM | SW | 栄養士 | 会計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 人数 | 40人〜50人 | 3〜5人 | 1〜2人 | 1人 | 1人 | 1人 |
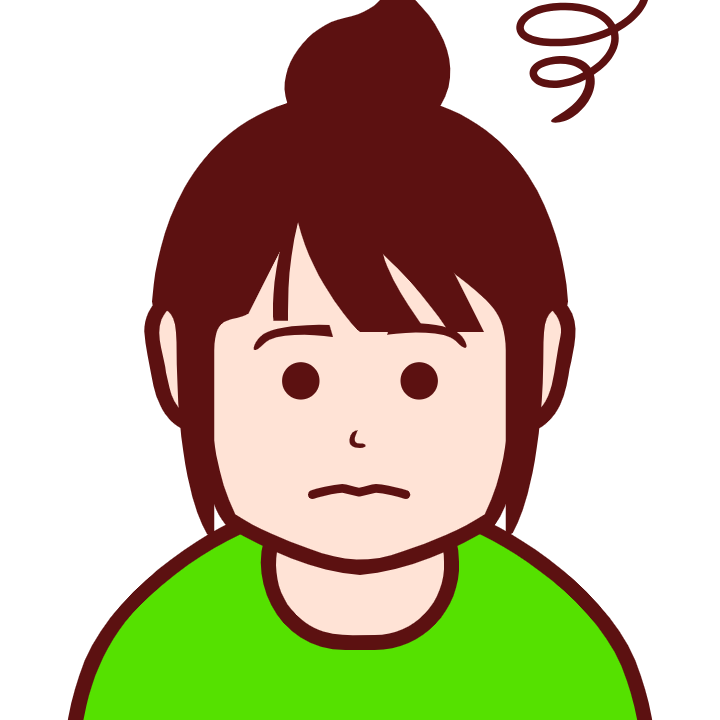
介護士以外は少数だね。
ひとり職場となるのはPT・OTだけじゃなのか。
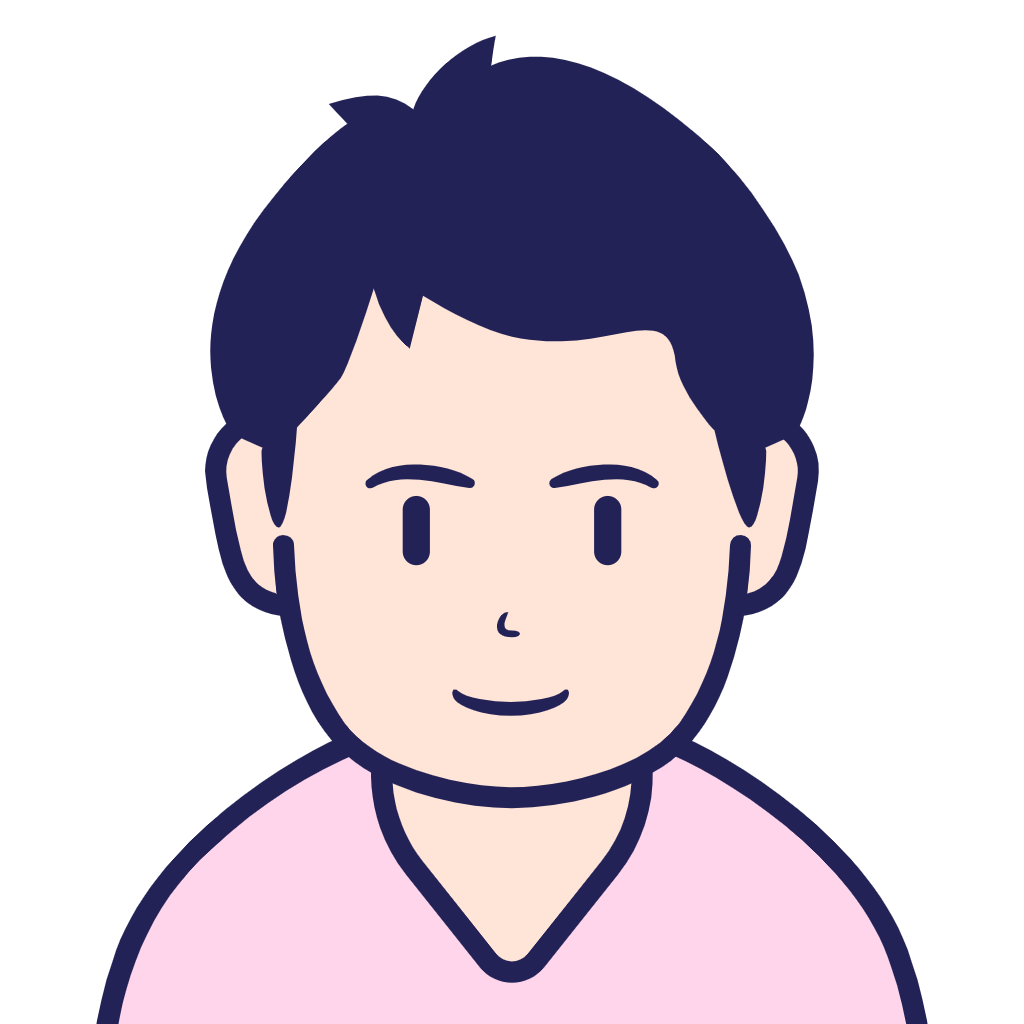
各職種の特養での役割とPT・OTとの関わりを紹介するよ!
治療がメインの病院と異なり、生活の場である特養では、介護士が主役だと言えます。
リハビリの頻度が少ない特養ではPT・OTにできることは限られています。
そのため、利用者の生活をより良いものにするためには介護士のサポートが不可欠。
介護士と良い関係性を築けなければ、特養ではPT・OTは無力だと言えます。
特養では医療的な処置は少なく、健康管理が主な仕事になります。
バイタルの異常や覚醒レベルに変化があれば、情報を共有し対応を決定します。
看護師とPT・OTは特養で唯一の医療職です。
そのため、感染症対策や褥瘡予防などで協力し合う機会が多くなります。
利用者一人ひとりの健康状態や嗜好を考慮した食事メニューを設計します。
日々の食事を観察し、味や形状を工夫して食欲が湧く工夫を考えています。
栄養士とは褥瘡予防で協力し合うことが多くなります。
除圧・栄養・処置という予防や治療に必要な3つを、栄養士・看護師とともに考えます。
利用者が安心して生活するためのケアプランを作成します。
必要な介護サービスを提供するために、職種間の連携を図ります。
PT・OTは、利用者の転倒リスクやADLの低下があればCMに報告を上げます。
CMは、多職種から集めた情報をもとに、家族へ情報提供を行います。
入退所のサポートや、入所後の利用者・家族の悩みを解決する支援を行います。
特養では、CMと相談員の仕事を大きく分けずに兼務している場合が多くあります。
PT・OTは、新しく入所する利用者の実態調査として相談員に同行します。
事前に利用者の様子を調査し、多職種で情報を共有します。
施設の収入・支出の管理や介護報酬請求業務を行います。
行政からの監査にも対応するため、加算に関する情報を積極的に収集しています。
特養では、リハビリの算定に必要な業務を自分ひとりで遂行する必要があります。
そのなかで、加算について知識をもっている会計は頼りになる存在。
算定条件をもれなく満たせるよう、日頃からこまめに確認しあいます。
職種・年齢の壁がない!特養ならではの人間関係
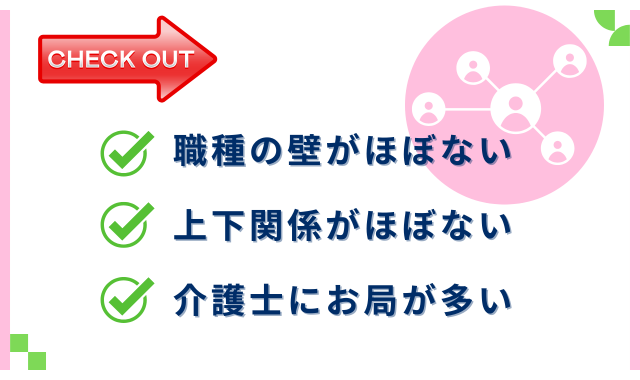
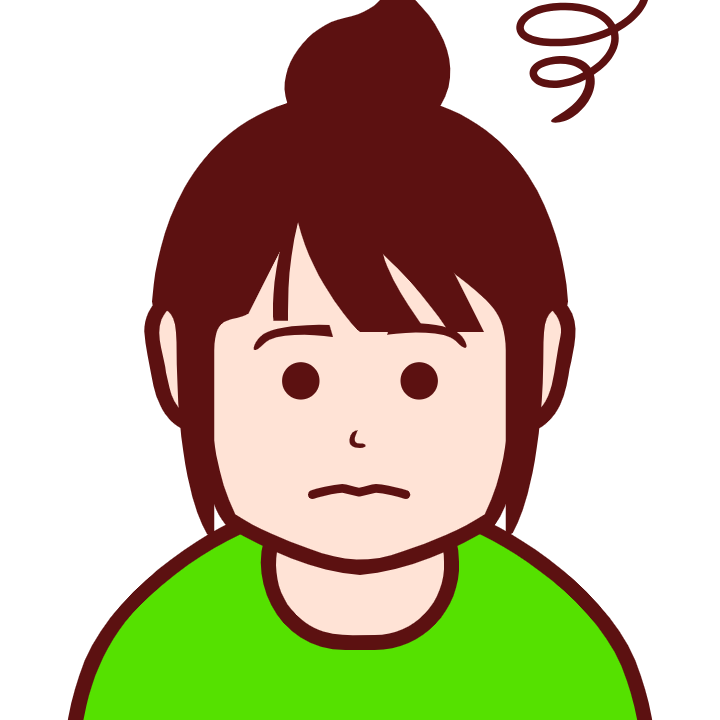
病院とは全然違う、人数構成になるんだね。
やっぱり関係性も変わるのかな?
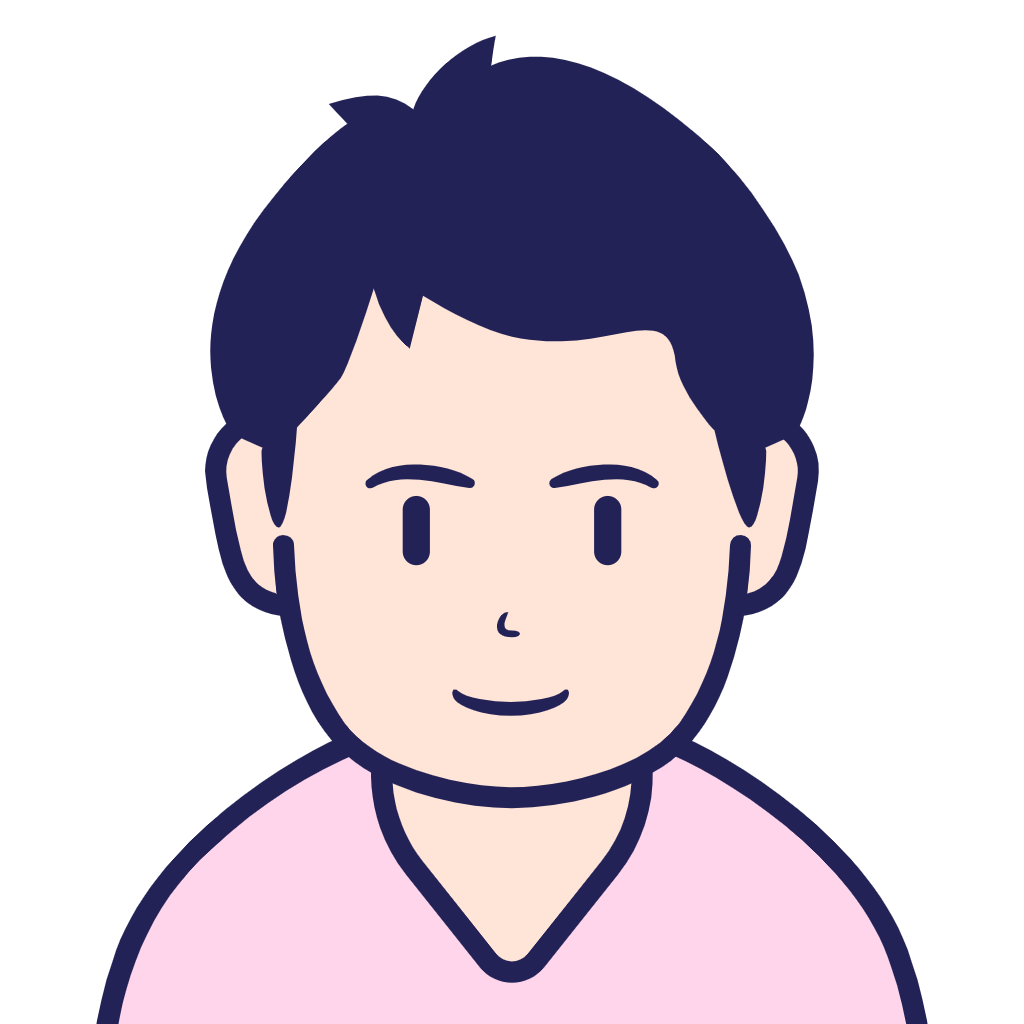
人間関係もまったく違ったものになるよ。
病院との違いを以下にまとめたよ♪
特養の特徴
- 職種間の壁がない
- 上下関係がない
- 介護士にお局あり
病院の特徴
- 同職種で仲が良い
- 上下関係あり
- 看護師にお局あり
特養における人間関係の特徴と、より良い人間関係を築くポイントについて紹介していきます!
職種間の壁がない理由は、ほとんどの職種が1〜5人の少数で構成されているから。
SW・CM・栄養士などひとり職種にとっては、誰と話をするにも相手が他職種になるのは当たりまえです。
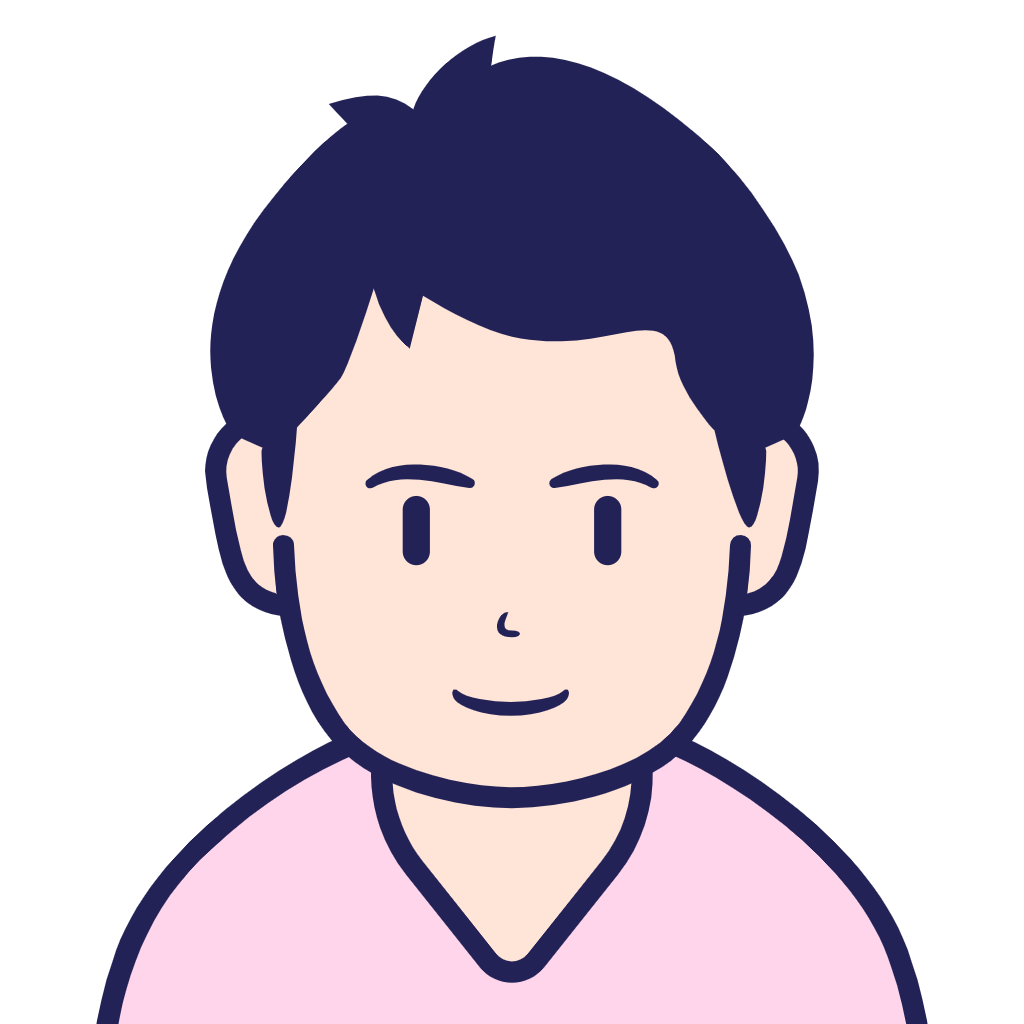
病院では、看護師に話しかけるにも勇気がいる場合もあるよね。
特養では、そういった感覚はなくなるよ。
そんな特養において、より良い人間関係を築くために守るべきポイントは、
やはり、それぞれ自分の職種にプライドをもっています。
そのため、自分の専門分野に他職種から意見を言われると気分を害してしまう可能性があります。
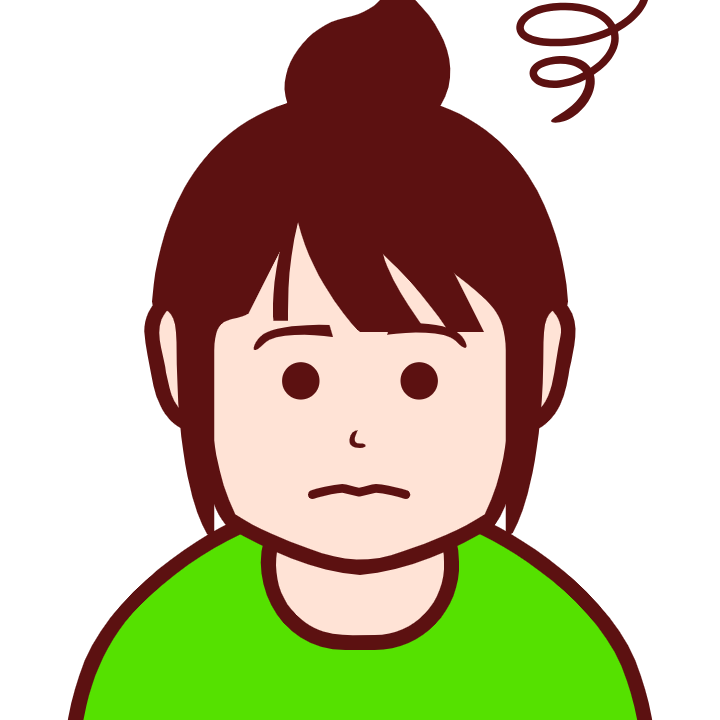
わざわざ他職種に口出しなんてしないよ!
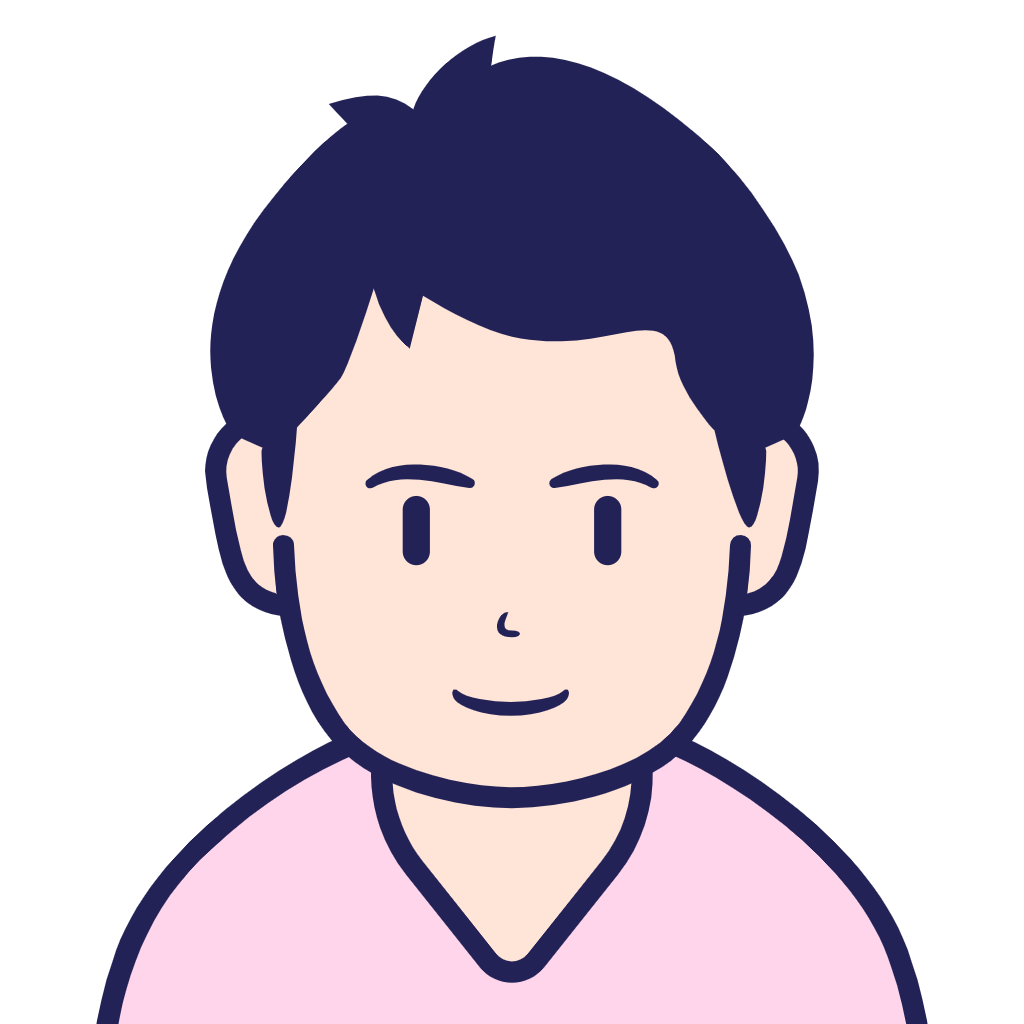
特養では他職種にも意見をしたくなる環境なんだよ。
他職種に意見をしたくなる理由は、各職種のレベルが個人の知識に大きく左右されるから。
例えば、病院での勤務経験のない看護師ばかり働く特養の場合。
利用者が急変した際、PT・OTは「血圧・脈拍・体温・SAT・呼吸数・視診・触診」で評価し、受診すべきだと判断。
しかし、看護師は「血圧・脈拍・体温」という不十分な評価だけで様子観察という判断をすることもあります。

呼吸数が異常だよ!?
様子を見ずに受診すべきでしょ!
もし、専門分野を超えて意見を言うのであれば、反発を受ける覚悟が必要です。
自分が意見をしなければ、
・施設に大きな損害をもたらす
・利用者にデメリットが生じる
・職員にデメリットが生じる
このような状況を除いて、相手の分野への口出しはNGです!
特養では先輩・後輩という上下関係は生じません。
上下関係が生じるのは、「教える側」と「教わる側」に分かれる場合だから。
特養では、お互いに職種が違うため「どっちが上だ下だ」という意識は働きません。
私が29歳で特養に転職したとき、周りはほぼ全員が年上でした。
それでも、当時から各職種の役職者でさえも、私のことを対等な立場として扱ってくれました。
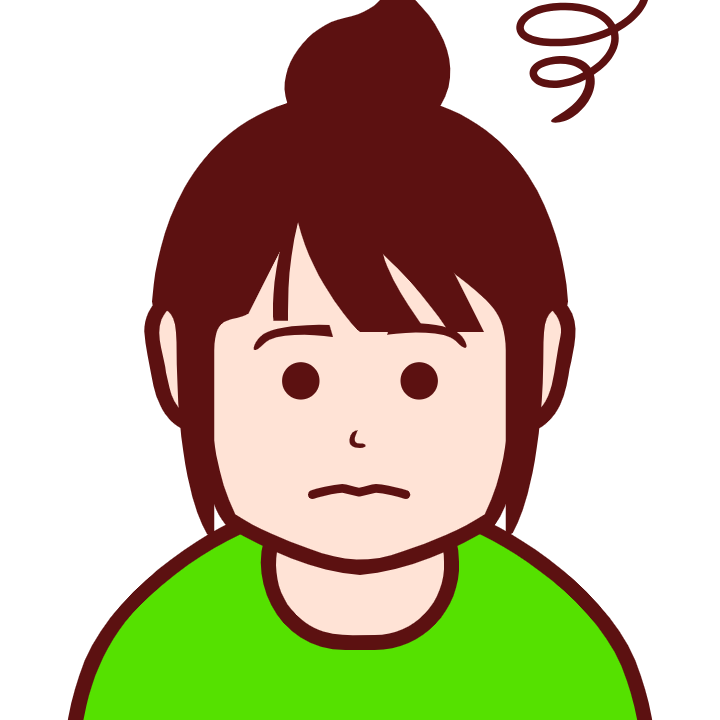
病院では、経験年数が自分より上の人は先輩になるよね。
自分よりも年下の人が先輩になることもあるし。
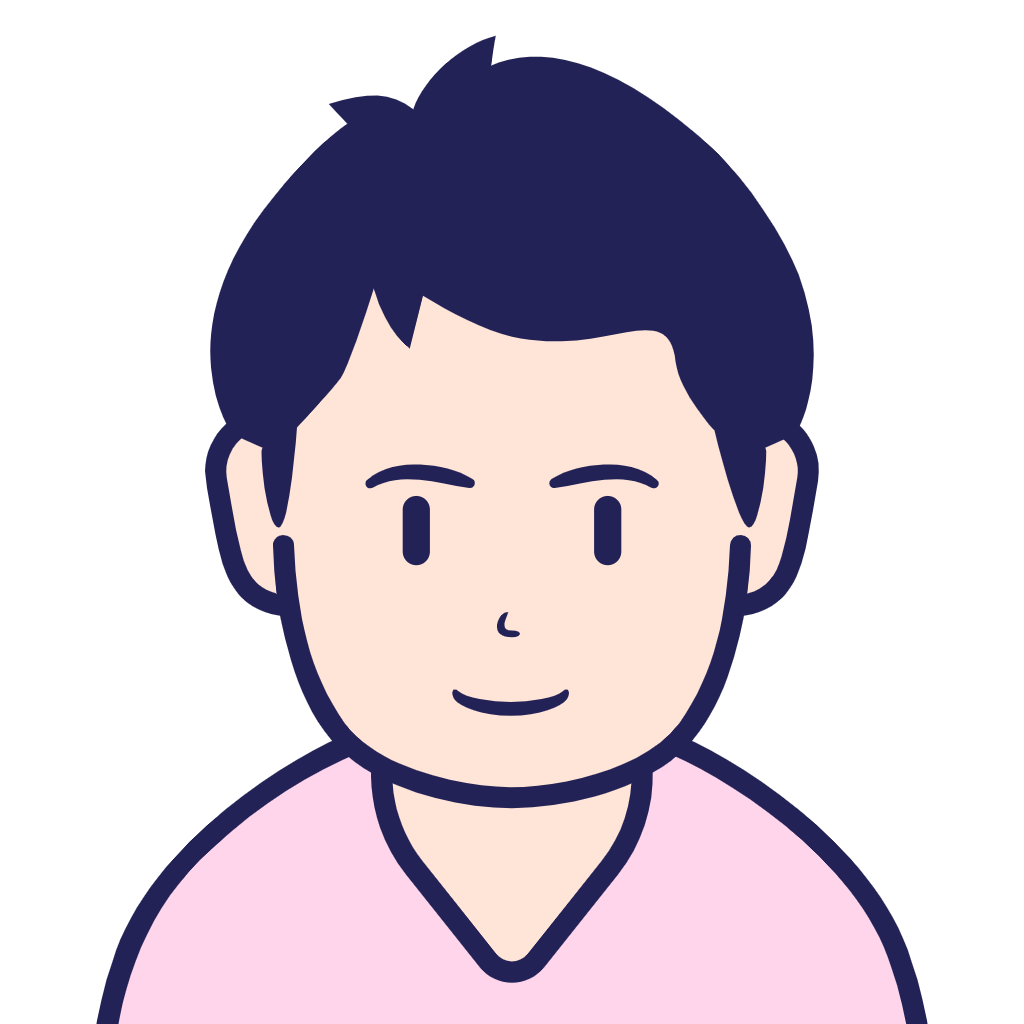
特養で上下関係がはっきりしているのは施設長・事務長くらいだね。
そんな特養において、より良い人間関係を築くために守るべきポイントは、
上下関係はなくても、年上には敬語を使うのが当たりまえ。
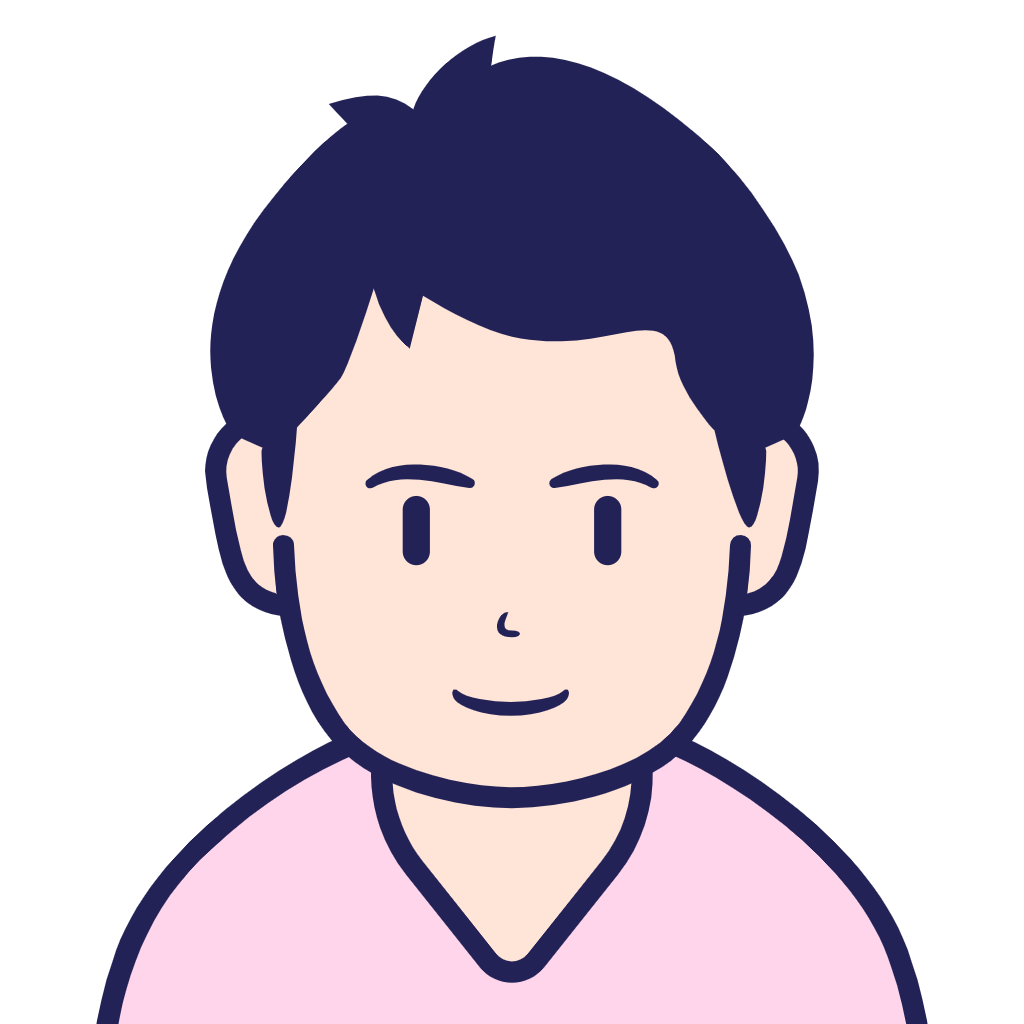
敬語さえ使っていれば、横一線の対等な立場として仕事を進めることができるよ♪
勤続年数が長いことで、職場で強い影響力をもつ「お局さん」。
特養では、介護士にお局がいることが多い!
理由は、介護士の数が多く勤続年数も長くなりやすい職場だから。
介護士の就職先でもっとも多いのは介護施設です。
| 高齢者福祉関係 | 障害者福祉関係 | 医療関係 | その他 |
|---|---|---|---|
| 81.8% | 9.4% | 6.1% | 2.4% |
【出典】「令和2年度社会福祉士・介護福祉士就労状況調査結果」
そのため、新卒で入職して15年〜20年も働き続けるような職員もいます。
機嫌が悪いことを隠さないため、怖くて誰も意見はできません。
そんな特養において、より良い人間関係を築くために守るべきポイントは、
介護士のお局さんには、看護師もリハ職も対抗できません。
「勤続年数」と「年齢」の両方でお局が上回ってしまうからです。
| 職種 | 介護士 | PT・OT | 看護師 |
|---|---|---|---|
| 平均年齢 | 50.0歳 | 34.7歳 | 41.9歳 |
正義感の強い人は、お局さんを正したくなる気持ちが湧いてくるかもしれません。
でも、それは絶対にNG!
お局さんに関わらず、「人を変えること」は不可能だから。
間違った意見や対応には、肯定も否定もせずやり過ごすのが一番。
あとは、直属の上司である介護主任に任せるしかありません!
【まとめ】フラットにコミュニケーションをとれる特養はPT・OTが働きやすい環境
特養でいっしょに働く職種は以下のとおり。
| 職種 | CW | NS | CM | SW | 栄養士 | 会計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 人数 | 40人〜50人 | 3〜5人 | 1〜2人 | 1人 | 1人 | 1人 |
病院とは異なり、介護士を除いて少数で構成されています。
そのため、人間関係も病院とは違ってきます。
特養の特徴
- 職種の壁がない
- 上下関係がない
- 介護士にお局あり
病院の特徴
- 同職種で仲が良い
- 上下関係あり
- 看護師にお局あり
他職種とのコミュニケーションが当たりまえの特養では、職種の壁はありません。
職種が違えば、経験年数は関係ないので、上下関係もありません。
そんな特養の人間関係は、内向的な私にはピッタリでした。
職種の壁や上下関係がないため、誰に話しかけるにも気構える必要がないから♪
もし、特養での仕事に興味をもった場合は、転職エージェントの利用をおすすめします。
希望条件にあった求人を紹介してくれ、給与交渉まで行ってもらえます♪
おすすめの転職エージェントは、以下の記事で紹介しています。
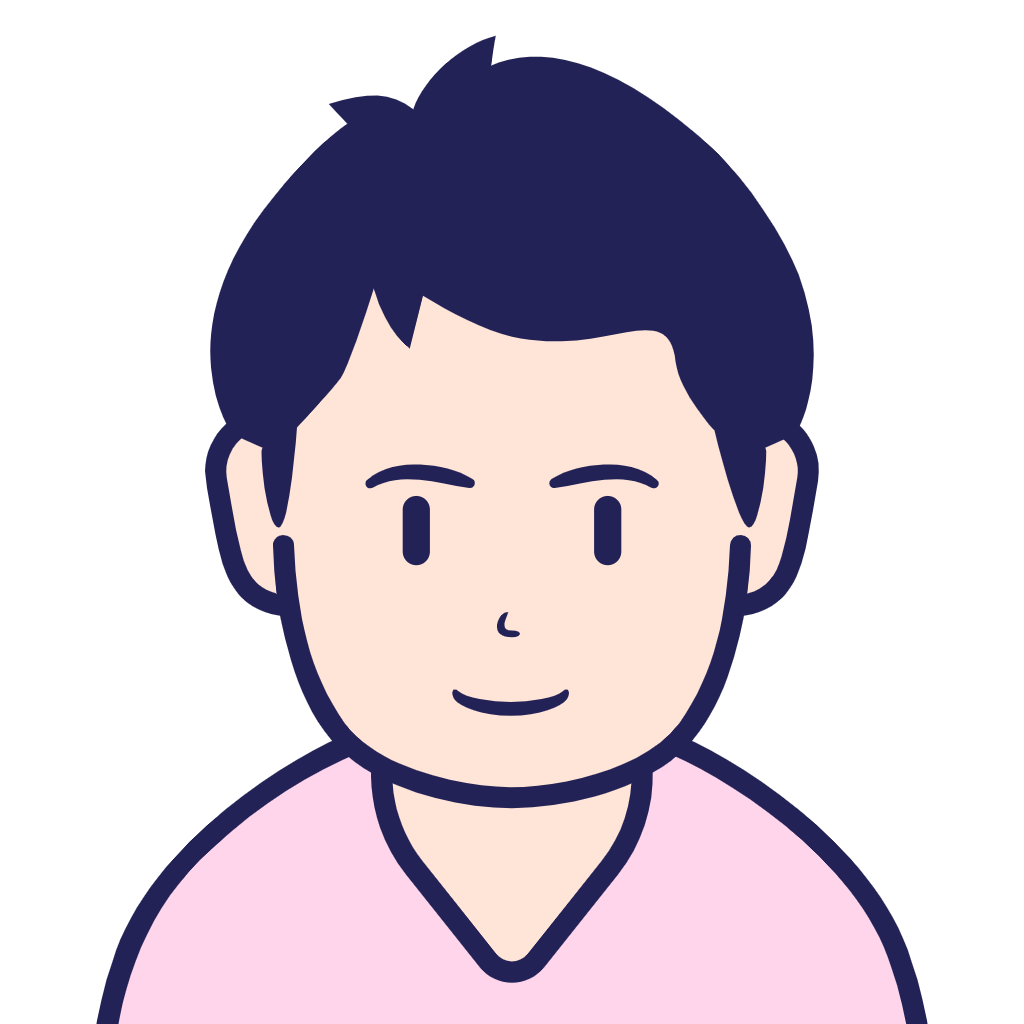
質問があれば、お問い合わせやエックスから気軽にご連絡ください♪
仕事内容や給料・休日に関しては、以下の記事を参考にしてください。